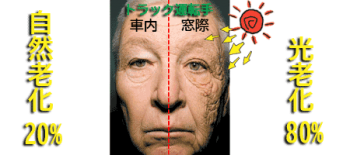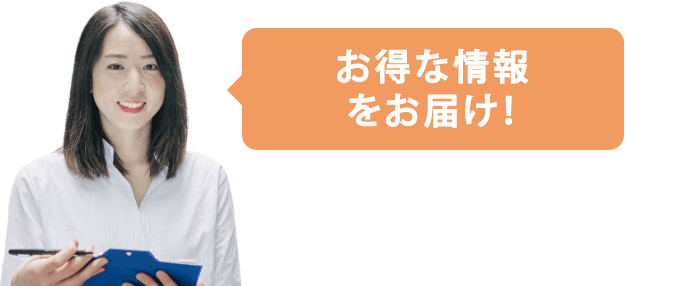健康ひろば
「マウスを強制冬眠」実験に成功。人間の人工冬眠実現に一歩前進

筑波大学の研究グループにより、マウスの脳を刺激することで冬眠に近い状態にすることに成功したと発表。
この研究結果は、本来は冬眠しない動物を人為的に冬眠させるこの実験の成功により、人間でも冬眠できる「人工冬眠」が実現し宇宙開発や医療、老化を遅らせる技術などに応用できると期待されています。
ヘビやカメといった「
この研究では「
この低温、低代謝状態では、体温と酸素消費量は非常に低く保たれますが、冬眠のように代謝を調節する機能は引き続き機能します。
また、回復後、組織や臓器への明らかな損傷や行動の異常はありませんでした。
つまり、研究結果では人間を含む本来は冬眠が出来ない哺乳類などへの潜在的な用途があります。
冬眠状態は低代謝状態となる能力は、老化や病気の進行を遅らせたりと、その潜在的医療進歩の可能性が持たれている。
医療だけでなく、SF映画などでよくみられる有人宇宙飛行船のコールドスリープも可能となるのではないでしょうか。

これまで動物の冬眠メカニズムは明確にされていませんでした。
その理由としては実験用として使用されるマウス等が冬眠をしないため、冬眠過程の観察(実験)が容易に出来ない点がありました。
そんな中、筑波大学医学医療系の医学博士で、睡眠研究の第一人者である櫻井武教授らの研究グループが、マウスを冬眠に似た状態に誘導できる新しい神経回路の特定に成功しました。
マウスの低体温、低代謝は、
・マウスの脳(視床下部)の一部に存在する神経細胞群を興奮させる。
*この神経細胞群をQ神経(Quiescence-inducing neurons : 休眠誘導神経)と名付けられた。
*この「Q神経」を刺激することにより生じる低代謝をQIH(Q neuron-induced hypometabolism)と名付けられた。
・この低代謝状態となったマウス(写真右側)は数日間動きが殆どなくなり、体温が著しく低下。

by 筑波大学 ↑通常 ↑低体温状態
この繰り返しの実験において冬眠(QIH)から復帰しても体に異常は見られませんでした。
このことから研究グループは、「QIHは野生動物が自然の中で行っている安全な冬眠に近い状態」だと考えています。
この研究では通常は冬眠をしない哺乳動物を冬眠状態へ誘導する事ができ、人間にも応用できる可能性があります。
現代の医学では治らない奇病が数年後の医療の進歩にかけて冬眠する時代が来るかもしれませんね。
研究を応援したいです。
参考研究経過:
・冬眠様状態を誘導する新規神経回路の発見 ~人工冬眠の実現へ大きな前進~(Backup)
参考資料: