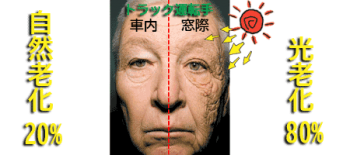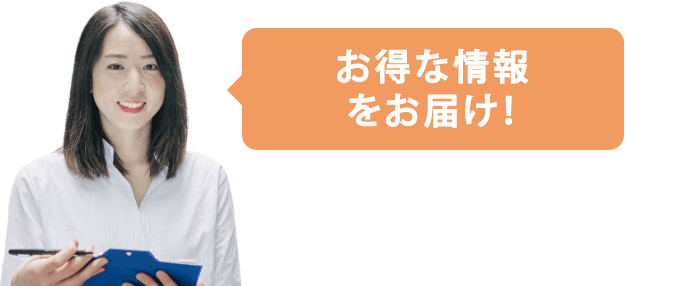健康ひろば
「風邪にはお粥」、日本の教えも 香港では、「いつでもお粥」 !

すでに立春が過ぎましたが、まだ肌寒い日が続いています。
今日は湿気たっぷりではありますが、
体調を崩して風邪をひかれている方も多いのではないでしょうか?
「風邪にはお粥」、このフレーズは誰しも聞いたことがありますよね。
弱った身体に、負担のかからないお粥は、
水分と栄養を、身体にすぐに届けてくれるし、
その温かさは、血液やリンパ液の流れをよくし、
健康的な免疫力を高めてくれます。
だから、小さな頃から「風邪にはお粥」だったんですね。
日本のお粥の定番
日本だと、風邪や病気の時など、身体が弱った時に食べるお粥ですが、
中国や香港では、通常でも普通にお粥を食べることがあります。
さすが、医食同源の国、常に身体のバランスをとるように個人個人が留意しているんですね。
中国や香港では、まだ起き抜けの朝にはお粥を食べることも多いですね。
広東式のお粥は、トロリとした米粒がすでになくなるほど炊き込んだものが主流で、
その中に、白身魚やミンチ肉、ピータンなどを入れて食べる。。。
う~ん、たまらなくお腹がすいてきました。
白粥と梅干が定番の日本ですが、
中国粥には、たくさんの具材にネギやショウガ、時にはピーナッツもはいり、
それだけ見ても、やはり「風邪にはお粥」ではなく、
「いつでもお粥」なんですね。
広東式のお粥は具材が多い!
もちろん、中国、香港でも、白身魚のお粥は、
病人食としても重要なポジションで、
テレビや映画で描かれる、病人への差し入れは白身魚のお粥やスープが多く見られます。’
今では、身体をリセットするためのファスティング(断食)後にも食べられるようですが
いずれにせよ、お粥にはどこか身体を浄化させるという意味あいもあるようですね。
新型肺炎(COVID-19) やインフルエンザが世界的な
猛威を振るう中、栄養補給も大切ですが、栄養を確実にとりいれることも大切。
疲れた身体に、さらりと確実に早く吸収されるお粥で
身体を健康に保つことがこの時期大切かもしれませんね。